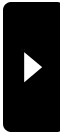2025年04月25日
早期経営改善計画、中小企業のリース会計と法人税
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2025年5月号 ★
若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年5月の税務
5月12日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請
6月2日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
資金繰りが苦しくなる前に〜早期経営改善計画〜
◆早期経営改善計画とは
企業の経営環境が厳しさを増す中、売上げの低迷や資金繰りの悪化に直面する前に手を打つことが求められています。そのための有効な手段が「早期経営改善計画」です。この制度は、国が認定する専門家のサポートを受けながら、自社のビジネスモデルや資金繰り計画を整理し、持続的な経営改善を図ることを目的としています。金融機関との対話を円滑に進め、経営の健全化を促すための重要なステップとなります。
◆制度を活用するメリット
早期経営改善計画の大きな魅力は、専門家の支援を受けながら計画を策定できる点です。通常、こうしたコンサルティングには費用がかかりますが、本制度を利用すれば、その費用の2/3(上限15万円)が補助されるため、負担を抑えながら取り組むことが可能です。さらに、経営状況を整理し、資金繰りの見直しを行うことで、金融機関との信頼関係を強化することもできます。
◆実際の活用方法
まず、認定支援機関と相談し、自社の経営課題を整理します。その上で、ビジネスモデルの現状を可視化し、具体的なアクションプランと資金繰り計画を策定。計画策定後も専門家が伴走支援を行い、計画の進捗状況を確認しながら必要な調整を行います。こうした継続的なフォローアップにより、策定した計画が実効性のあるものとなり、経営改善につながるのです。
◆成功事例の紹介
例えば、ある運送業のA社では、この制度を活用し、取引先ごとの利益率を分析しました。その結果、利益率の高い取引先を明確にし、重点的に対応することで収益の向上を図ることができました。また、資金繰り計画を作成したことで、経営状況を数値で把握しやすくなり、金融機関との交渉もスムーズに進むようになりました。更に、後継者が財務管理の手法を学ぶ機会にもなり、経営の安定化に大きく貢献しました。
◆最新の動向と今後の展望
2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、本制度の取扱期間が2028年1月まで延長されました。自社の経営を立て直し、持続的な成長を実現するため、この機会に早期経営改善計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。
中小企業のリース会計と法人税
◆リースとは所有せずに使用する契約
リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約をいいます。契約期間にわたり支払を分散させることができます。
ファイナンス・リースは中途解約できない代わりにリース資産を使用して経済的利益を受けることができ、リース期間終了までリース料を支払うもの、オペレーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。
◆上場会社等のリース会計は売買処理に統一
上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、ファイナンス・リースはリース資産を売買があったものとして資産として計上します(売買処理)。オペレーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、新リース会計基準の適用により資産計上(売買処理)となりました。
◆中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま
中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール(中小企業会計指針、中小企業会計要領)によることができ、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースともに賃貸借処理が適用できます。新リース会計基準は強制適用されず、従来どおり賃貸借処理が継続できます。
◆上場会社等の法人税の扱い
上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、少額リース、短期リースを除き、売買処理が適用されます。このうち所有権移転外リースについては資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。一方、オペレーティング・リースを受けた場合は賃貸借処理が適用されます。会計では元本部分と利息部分を分けて処理するので法人税の処理と一致しなくなり、申告調整が必要となります。
◆中小企業の法人税は賃貸借処理のまま
中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され、賃借料として損金経理した場合はリース資産の償却費とみなして損金に算入されます。
また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後も賃貸借処理が継続されます。令和7年度税制改正大綱では、オペレーティング・リースで法人が支払うリース料について「債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、この文言から従来の賃貸借処理のままとなると解されます。
若葉が目にまぶしい季節になりました。
季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年5月の税務
5月12日
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
5月15日
●特別農業所得者の承認申請
6月2日
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)
資金繰りが苦しくなる前に〜早期経営改善計画〜
◆早期経営改善計画とは
企業の経営環境が厳しさを増す中、売上げの低迷や資金繰りの悪化に直面する前に手を打つことが求められています。そのための有効な手段が「早期経営改善計画」です。この制度は、国が認定する専門家のサポートを受けながら、自社のビジネスモデルや資金繰り計画を整理し、持続的な経営改善を図ることを目的としています。金融機関との対話を円滑に進め、経営の健全化を促すための重要なステップとなります。
◆制度を活用するメリット
早期経営改善計画の大きな魅力は、専門家の支援を受けながら計画を策定できる点です。通常、こうしたコンサルティングには費用がかかりますが、本制度を利用すれば、その費用の2/3(上限15万円)が補助されるため、負担を抑えながら取り組むことが可能です。さらに、経営状況を整理し、資金繰りの見直しを行うことで、金融機関との信頼関係を強化することもできます。
◆実際の活用方法
まず、認定支援機関と相談し、自社の経営課題を整理します。その上で、ビジネスモデルの現状を可視化し、具体的なアクションプランと資金繰り計画を策定。計画策定後も専門家が伴走支援を行い、計画の進捗状況を確認しながら必要な調整を行います。こうした継続的なフォローアップにより、策定した計画が実効性のあるものとなり、経営改善につながるのです。
◆成功事例の紹介
例えば、ある運送業のA社では、この制度を活用し、取引先ごとの利益率を分析しました。その結果、利益率の高い取引先を明確にし、重点的に対応することで収益の向上を図ることができました。また、資金繰り計画を作成したことで、経営状況を数値で把握しやすくなり、金融機関との交渉もスムーズに進むようになりました。更に、後継者が財務管理の手法を学ぶ機会にもなり、経営の安定化に大きく貢献しました。
◆最新の動向と今後の展望
2024年11月に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」により、本制度の取扱期間が2028年1月まで延長されました。自社の経営を立て直し、持続的な成長を実現するため、この機会に早期経営改善計画の策定を検討してみてはいかがでしょうか。
中小企業のリース会計と法人税
◆リースとは所有せずに使用する契約
リースは他人から特定の資産を一定期間、リース料を支払って使用する契約をいいます。契約期間にわたり支払を分散させることができます。
ファイナンス・リースは中途解約できない代わりにリース資産を使用して経済的利益を受けることができ、リース期間終了までリース料を支払うもの、オペレーティング・リースはファイナンス・リース以外のリースをいいます。
◆上場会社等のリース会計は売買処理に統一
上場会社等のリース取引に適用される会計基準は、ファイナンス・リースはリース資産を売買があったものとして資産として計上します(売買処理)。オペレーティング・リースはこれまで賃貸借として扱っていましたが、新リース会計基準の適用により資産計上(売買処理)となりました。
◆中小企業のリース会計は賃貸借処理のまま
中小企業のリース会計は、中小企業向けの会計ルール(中小企業会計指針、中小企業会計要領)によることができ、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースともに賃貸借処理が適用できます。新リース会計基準は強制適用されず、従来どおり賃貸借処理が継続できます。
◆上場会社等の法人税の扱い
上場会社等がファイナンス・リースを受けた場合の法人税の扱いは、少額リース、短期リースを除き、売買処理が適用されます。このうち所有権移転外リースについては資産計上額をリース期間にわたり月数按分で減価償却します。一方、オペレーティング・リースを受けた場合は賃貸借処理が適用されます。会計では元本部分と利息部分を分けて処理するので法人税の処理と一致しなくなり、申告調整が必要となります。
◆中小企業の法人税は賃貸借処理のまま
中小企業のファイナンス・リースに係る法人税の扱いは賃貸借処理が適用され、賃借料として損金経理した場合はリース資産の償却費とみなして損金に算入されます。
また、オペレーティング・リースに係る法人税は、新リース会計基準の導入後も賃貸借処理が継続されます。令和7年度税制改正大綱では、オペレーティング・リースで法人が支払うリース料について「債務の確定した部分の金額は、その確定した日の属する事業年度に損金算入する」と記載されており、この文言から従来の賃貸借処理のままとなると解されます。
2025年03月25日
決算書分析、組織再編税制と適格現物分配
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2025年4月号 ★
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
少しだけ思い入れのある春、3月25日です。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年4月の税務
4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう
◆決算書=事業の成績表を分析してますか?
決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合は暦年決算なので、1〜2月頃には前年の成績表ができているでしょう。決算書をどう見ていますか。単に前年より増えた減っただけで終わっていませんか。
もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比べ、自社の強みと弱みをしっかりと認識するところまで、決算成績表を活用してみませんか。
◆自業種での適正な原価率・人件費率等は?
飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件費」の「売上高」に占める割合を「FL比率:F=Food、L=Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60%以下といわれています。FL以外の経費(店舗家賃、水道光熱費、機器のリース料など)が30%超えることが多いため、FL比率が70%を超えてくると、利益がほとんど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲食店経営においては、FL比率を常に把握し、改善をしてゆくことが、経営を安定させることにつながります。
◆利益増は売上増か経費の削減
利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その両方かということになります。
売上=客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価を増やすには、どんな方法がありそうですか。座席数を増やせないか、回転率を上げられないか、客単価を増やすには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデアがいくつか出てくるでしょう。
経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れにつながるので、ムダがないかの検証が必要です。同じ食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなっていませんか。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといって近所のお店で一般消費者と同じ値段で購入などしていませんか。食材ロスの減少はできそうですか。また、常連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっていませんか。こうしたものがあれば即見直しが必要です。
人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。効率的な動き方の業務マニュアルの作成などでムダな人件費の発生の抑制も目指しましょう。
数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの利益が残るような成果につなげてください。
組織再編税制と適格現物分配
◆組織再編制度としての現物分配
法人が株主に対し配当により金銭以外の資産を交付することを会社法では現物配当と言っていますが、法人税法はこれを、現物分配と規定し組織再編行為としています。その結果、現物分配は、組織再編による資産の譲渡と認識されることになります。
また、100%完全支配関係での現物分配は適格現物分配と規定され、適格現物分配での資産の移転価額は、移転直前の帳簿価額に拠るものとされ、譲渡損益は生じないことになっています。
◆配当の仲間から排除しての益金不算入
適格現物分配は、法人税法上、受取配当金の仲間から除外されています。その結果、完全子法人株式・関連法人株式に係る配当計算期間における継続保有規定での適用制限要件から解放されています。さらに、適格現物分配は、所得税法上の配当所得からも除外され、その結果、配当所得に係る源泉徴収の対象から除外されてもいます。
なお、適格現物分配は、利益積立金の増加項目として政令に特記されています。会計上収益計上されている受取配当金は、従って実務的には、法人税申告書別表四において「適格現物分配に係る益金不算入額」として減算・社外流出処理をすることになります。
◆適格現物分配と継続要件
組織再編税制における適格要件では、100%の持株関係という完全支配関係の継続が見込まれていること、と規定されるものが多いのですが、適格現物分配制度では、現物分配を行う直前での完全支配関係だけで十分で、継続要件は置かれていません。
◆現物分配と消費税
現物分配は、配当という手段で不動産や株式などの金銭以外の資産を交付することなので、資産の譲渡の概念に含まれる、と言えます。しかし、資産の譲渡の概念に含まれるとしても、必ずしも消費税の課税対象になる、というわけではありません。
対価を得て行う事業行為であれば消費税の課税対象となる資産の譲渡等に該当することになりますが、現物分配は株主の地位に基づく、出資への謝礼として分配されるものなので、消費税法上の資産の譲渡等には該当せず、不課税となります。
花便りが各地から聞こえてくる季節となりました。
新しい生活が実り多きものになりますようお祈りいたしております。
少しだけ思い入れのある春、3月25日です。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年4月の税務
4月10日
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
4月15日
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出
4月30日
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○軽自動車税(種別割)の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付(4月中において市町村の条例で定める日)
○固定資産課税台帳の縦覧期間(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの期間等)
事業の成績表の分析で利益を多く残す工夫につなげましょう
◆決算書=事業の成績表を分析してますか?
決算書は一年間の事業の成績表です。個人事業の場合は暦年決算なので、1〜2月頃には前年の成績表ができているでしょう。決算書をどう見ていますか。単に前年より増えた減っただけで終わっていませんか。
もう少しだけ比較対象を拡げ、同規模の同業他社と比べ、自社の強みと弱みをしっかりと認識するところまで、決算成績表を活用してみませんか。
◆自業種での適正な原価率・人件費率等は?
飲食店経営の場合を例にします。「食材費」と「人件費」の「売上高」に占める割合を「FL比率:F=Food、L=Labor」といい、一般的にFL比率の適正値は60%以下といわれています。FL以外の経費(店舗家賃、水道光熱費、機器のリース料など)が30%超えることが多いため、FL比率が70%を超えてくると、利益がほとんど残らなくなり、立ち行かなくなります。そのため、飲食店経営においては、FL比率を常に把握し、改善をしてゆくことが、経営を安定させることにつながります。
◆利益増は売上増か経費の削減
利益増には、売上を増やすか、経費を減らすか、その両方かということになります。
売上=客数×客単価です。あなたのお店で客数・単価を増やすには、どんな方法がありそうですか。座席数を増やせないか、回転率を上げられないか、客単価を増やすには何か策がないか等々、検討し実行すべきアイデアがいくつか出てくるでしょう。
経費の削減については、食材費の質を落とすと客離れにつながるので、ムダがないかの検証が必要です。同じ食材でも購入方法いかんで仕入額が高くなっていませんか。業務卸店で仕入れるのではなく、面倒だからといって近所のお店で一般消費者と同じ値段で購入などしていませんか。食材ロスの減少はできそうですか。また、常連客へのサービスとして盛りを大きくして原価増となっていませんか。こうしたものがあれば即見直しが必要です。
人材配置も過剰に心配して厚く集めすぎていませんか。効率的な動き方の業務マニュアルの作成などでムダな人件費の発生の抑制も目指しましょう。
数字を比較・分析して、いろいろな工夫をし、多くの利益が残るような成果につなげてください。
組織再編税制と適格現物分配
◆組織再編制度としての現物分配
法人が株主に対し配当により金銭以外の資産を交付することを会社法では現物配当と言っていますが、法人税法はこれを、現物分配と規定し組織再編行為としています。その結果、現物分配は、組織再編による資産の譲渡と認識されることになります。
また、100%完全支配関係での現物分配は適格現物分配と規定され、適格現物分配での資産の移転価額は、移転直前の帳簿価額に拠るものとされ、譲渡損益は生じないことになっています。
◆配当の仲間から排除しての益金不算入
適格現物分配は、法人税法上、受取配当金の仲間から除外されています。その結果、完全子法人株式・関連法人株式に係る配当計算期間における継続保有規定での適用制限要件から解放されています。さらに、適格現物分配は、所得税法上の配当所得からも除外され、その結果、配当所得に係る源泉徴収の対象から除外されてもいます。
なお、適格現物分配は、利益積立金の増加項目として政令に特記されています。会計上収益計上されている受取配当金は、従って実務的には、法人税申告書別表四において「適格現物分配に係る益金不算入額」として減算・社外流出処理をすることになります。
◆適格現物分配と継続要件
組織再編税制における適格要件では、100%の持株関係という完全支配関係の継続が見込まれていること、と規定されるものが多いのですが、適格現物分配制度では、現物分配を行う直前での完全支配関係だけで十分で、継続要件は置かれていません。
◆現物分配と消費税
現物分配は、配当という手段で不動産や株式などの金銭以外の資産を交付することなので、資産の譲渡の概念に含まれる、と言えます。しかし、資産の譲渡の概念に含まれるとしても、必ずしも消費税の課税対象になる、というわけではありません。
対価を得て行う事業行為であれば消費税の課税対象となる資産の譲渡等に該当することになりますが、現物分配は株主の地位に基づく、出資への謝礼として分配されるものなので、消費税法上の資産の譲渡等には該当せず、不課税となります。
2025年02月25日
令和7年度税制改正大綱 個人所得課税編、企業年金・個人年金
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2025年3月号 ★
春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年3月の税務
3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月17日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月2日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
企業年金・個人年金
◆日本の年金制度は3階建て
現在の年金制度は1・2階は公的年金で老後生活の基本を支え、3階の企業年金、個人年金と合わせて、多様な希望、ニーズに対応しています。企業年金、個人年金の種類や税制の優遇措置について多岐に分かれています。
1.企業年金と個人年金
企業が従業員のために実施する「企業年金」は退職金の分割とも言える外部積み立ての退職給付制度として発展してきました。一方、個人が自ら加入する「個人年金」は公的年金に加えて老後の所得を確保、補填したい人の自助努力を支援する制度です。
2023年の常用労働者30人以上の企業の調査で退職年金制度がある23.2%、退職一時金のみは51.7%、退職給付制度がないは24.8%でした。
税法上の優遇制度があり、拠出時と運用時は原則非課税です。年金として受給する場合は「公的年金にかかる雑所得」として「公的年金等控除」を差し引いた額が所得税・住民税の課税対象です。一時金として受給する場合は「退職手当等」に該当し、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引いた額の2分の1が課税対象です。
2.「確定給付型と」「確定拠出型」
企業年金・個人年金のうち「確定給付型」は加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっています。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、運用状況の悪化などで資産の積み立て不足が発生する場合があり、その時は事業主が掛金を拠出して不足分を埋める必要があります。
「確定拠出型」はあらかじめ定められた拠出額とその運用収益との合計額を基に個人別に年金給付をします。加入者個々人が運用方法を選択し、運用結果は個人に帰着し、額が決定されます。
3.確定給付型年金
確定給付型企業年金(DB)は適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として2001年創設されました。事業主が掛金を拠出し事業主掛金は全額非課税ですが、加入者掛金は民間の個人年金と同じ扱いで他の生命保険料と合算して年4万円を上限に生命保険料控除となります。
また、厚生年金基金は厚生年金の一部を代行していましたが、多くは他の制度へ移行が進んでいます。
令和7年度税制改正大綱 個人所得課税編
◆基礎控除と給与所得控除は10万円引上げ
物価上昇局面の税負担調整、就業調整への対応措置として基礎控除は合計所得金額2,350万円以下の控除額を10万円引き上げて58万円に、給与所得控除は55万円の最低保障額を65万円に引き上げ、給与収入123万円まで課税されなくなります。令和7年分以後の所得税に適用されます。
◆大学生年代の親族の扶養控除枠を拡大
大学生アルバイトの就業調整に対応して19歳以上23歳未満の子等で合計所得金額123万円以下、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、給与収入150万円までは63万円を控除し、さらに給与収入が増えると段階的に控除額を削減する特定親族特別控除(仮称)が、令和7年分以後の所得税に適用されます。
◆扶養控除、同一生計配偶者の要件も引上げ
基礎控除の引上げに伴い、人的控除が見直されます。扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下となり、現行48万円から10万円引き上げられます。
個人住民税も給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設、扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件等を改正し、令和8年分から適用されます。
◆iDeCoの拠出限度額を引上げ
iDeCoは加入年齢を70歳未満に引き上げ、拠出限度額は自営業者等は月額7.5万円(現行:月額6.8万円)、企業年金加入者は月額6.2万円から確定給付企業年金の掛金額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)、企業年金未加入者は月額6.2万円(現行:月額2.3万円)に引き上げ、全額所得控除されます。
◆子育て世帯への支援措置を1年継続・拡充
(1)住宅ローン控除
住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)、および床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下、40㎡以上)は令和7年限り適用されます。
(2)住宅リフォーム税制(継続)
工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除する措置が令和7年限り適用されます。
(3)生命保険料控除(拡充)
新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族のある場合、令和8年分の適用限度額を6万円(現行4万円)に引き上げます(合計適用限度額12万円)。
春の陽気が待ち遠しい今日この頃、いかがお過ごしですか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年3月の税務
3月10日
●2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
3月17日
●前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
●前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
●所得税確定損失申告書の提出
●前年分所得税の総収入金額報告書の提出
●確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月2日)
●個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
●個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
3月31日
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者(前年12月分及び当年1月分)の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
企業年金・個人年金
◆日本の年金制度は3階建て
現在の年金制度は1・2階は公的年金で老後生活の基本を支え、3階の企業年金、個人年金と合わせて、多様な希望、ニーズに対応しています。企業年金、個人年金の種類や税制の優遇措置について多岐に分かれています。
1.企業年金と個人年金
企業が従業員のために実施する「企業年金」は退職金の分割とも言える外部積み立ての退職給付制度として発展してきました。一方、個人が自ら加入する「個人年金」は公的年金に加えて老後の所得を確保、補填したい人の自助努力を支援する制度です。
2023年の常用労働者30人以上の企業の調査で退職年金制度がある23.2%、退職一時金のみは51.7%、退職給付制度がないは24.8%でした。
税法上の優遇制度があり、拠出時と運用時は原則非課税です。年金として受給する場合は「公的年金にかかる雑所得」として「公的年金等控除」を差し引いた額が所得税・住民税の課税対象です。一時金として受給する場合は「退職手当等」に該当し、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引いた額の2分の1が課税対象です。
2.「確定給付型と」「確定拠出型」
企業年金・個人年金のうち「確定給付型」は加入期間などに基づいてあらかじめ給付の算定方法が決まっています。加入者が高齢期の生活設計を立てやすい反面、運用状況の悪化などで資産の積み立て不足が発生する場合があり、その時は事業主が掛金を拠出して不足分を埋める必要があります。
「確定拠出型」はあらかじめ定められた拠出額とその運用収益との合計額を基に個人別に年金給付をします。加入者個々人が運用方法を選択し、運用結果は個人に帰着し、額が決定されます。
3.確定給付型年金
確定給付型企業年金(DB)は適格退職年金や厚生年金基金を承継した給付建ての企業年金制度として2001年創設されました。事業主が掛金を拠出し事業主掛金は全額非課税ですが、加入者掛金は民間の個人年金と同じ扱いで他の生命保険料と合算して年4万円を上限に生命保険料控除となります。
また、厚生年金基金は厚生年金の一部を代行していましたが、多くは他の制度へ移行が進んでいます。
令和7年度税制改正大綱 個人所得課税編
◆基礎控除と給与所得控除は10万円引上げ
物価上昇局面の税負担調整、就業調整への対応措置として基礎控除は合計所得金額2,350万円以下の控除額を10万円引き上げて58万円に、給与所得控除は55万円の最低保障額を65万円に引き上げ、給与収入123万円まで課税されなくなります。令和7年分以後の所得税に適用されます。
◆大学生年代の親族の扶養控除枠を拡大
大学生アルバイトの就業調整に対応して19歳以上23歳未満の子等で合計所得金額123万円以下、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、給与収入150万円までは63万円を控除し、さらに給与収入が増えると段階的に控除額を削減する特定親族特別控除(仮称)が、令和7年分以後の所得税に適用されます。
◆扶養控除、同一生計配偶者の要件も引上げ
基礎控除の引上げに伴い、人的控除が見直されます。扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下となり、現行48万円から10万円引き上げられます。
個人住民税も給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設、扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件等を改正し、令和8年分から適用されます。
◆iDeCoの拠出限度額を引上げ
iDeCoは加入年齢を70歳未満に引き上げ、拠出限度額は自営業者等は月額7.5万円(現行:月額6.8万円)、企業年金加入者は月額6.2万円から確定給付企業年金の掛金額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)、企業年金未加入者は月額6.2万円(現行:月額2.3万円)に引き上げ、全額所得控除されます。
◆子育て世帯への支援措置を1年継続・拡充
(1)住宅ローン控除
住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)、および床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下、40㎡以上)は令和7年限り適用されます。
(2)住宅リフォーム税制(継続)
工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除する措置が令和7年限り適用されます。
(3)生命保険料控除(拡充)
新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族のある場合、令和8年分の適用限度額を6万円(現行4万円)に引き上げます(合計適用限度額12万円)。
2025年01月23日
相続放棄、年金と税制
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2025年2月号 ★
寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬようお気を付けください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
相続放棄の手続きの実際とその流れ
◆相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
◆相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
◆相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。
年金と税制
◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。
◆公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。
◆老齢年金でも一定額以下は非課税
単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。
住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。
寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。
お風邪など召しませぬようお気を付けください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年2月の税務
2月10日
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2月28日
●12月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○前年分贈与税の申告(申告期間:2月3日から3月17日まで)
○前年分所得税の確定申告(申告期間:2月17日から3月17日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付(2月中において市町村の条例で定める日)
相続放棄の手続きの実際とその流れ
◆相続における3つの選択
相続が発生すると相続人となる者は、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)、もしくは限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)、または相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)のいずれかを選ぶことになります。
相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、借金がなくとも相続にかかわりたくない、財産分与ゼロでハンコを押すのはしゃくだなど、他の理由であっても自分の意思で選べます。
◆相続放棄の手順
(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならないと定められています。申述書に申述内容を記入し、被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して家庭裁判所に書類を送ります。
(2)家庭裁判所から「照会書」が届く
申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、①誰かに強要されたり、②他人が勝手に手続きしたり、③相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。
書類をよく読んで、真意である旨を「回答書」に自筆で記載し期限内に返送します。
(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了
家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)が届いて手続き完了となります。
なお、他の相続人が相続手続きをする際に「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、事前に受理証明書の交付申請を行えば受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。
◆相続放棄のデメリット
相続放棄が完了すると後から撤回できないため、相続放棄完了後に莫大な財産が見つかったとしても、その財産を引き継ぐことはできません。また、他にも個々の事情で発生するデメリットもあり得ます。放棄に際しては、司法書士などの専門家に相談しながら手続きすることをお勧めします。
年金と税制
◆老齢年金は課税、障害・遺族年金は非課税
公的年金給付は受給権者の生活の安定のため、支給を受けた金額が租税等の課税対象とならぬよう課税対象から外されています。ただし例外的に老齢年金は課税対象とされています。これは、老齢への備えとして保険料納付実績に比例した給付であり、一種の貯蓄的な性格や給与の後払い的な性格があること、保険加入中に被保険者として納付した保険料は社会保険料控除として拠出段階ですでに非課税であること等を勘案したものとされています。
障害年金と遺族年金はあらかじめ発生を予期できないリスクに対応して給付を行うもので非課税とされています。
◆公的年金は公的年金控除の対象
公的年金等の収入は雑所得に区分され、公的年金等控除額を差し引いて、所得金額を計算します。公的年金控除の額は定額控除40万円と定率控除(50万円を差し引いた後の年金の収入に応じて、25%、15%、5%と段階的に減少)を合計し、合計額と最低保障額(国民年金基金、65歳以上は110万円、65歳未満は60万円)の大きい方の額になります。
公的年金控除は基礎年金、厚生年金、厚生年金基金、国民年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)等が対象です。
◆老齢年金でも一定額以下は非課税
単身者で公的年金控除の最低保障額110万円と基礎控除48万円に支払った医療保険料、介護保険料等の社会保険料控除を加えた額が所得年金収入158万円に社会保険料の額を加えた額以下の場合は、課税所得がないので所得税は非課税になります。
住民税を見ると公的年金等控除最低保障額110万円を差し引いた額が均等割り非課税基準以下の場合は非課税です。非課税基準は自治体により異なりますが、東京23区や指定都市の基準は同じです。
年金に所得税がかかる場合は、日本年金機構が年金支給額から所得税を源泉徴収して国に納付します。公的年金等以外の所得が20万円を超える場合や公的年金等の収入が400万円を超える場合は確定申告が必要です。
2025年01月01日
紅白2024 謹賀新年
謹賀新年
皆さまにとって2025年がいい年になりますように。
大晦日の紅白歌合戦、録画で高橋真梨子、矢野顕子&MISIAを見ました。
矢野顕子&MISIAの歌は希望に満ちていました。
高橋真梨子と矢野顕子は、私の車の中でよくかかります。
2人とも、20代からの大切なアーティストです。
高橋真梨子は、20歳の時、筑紫哲也さんの著書の中で知りました。
元旦は、穏やかな一日となりました。
この穏やかさが、一年続くといいですね。
皆さまにとって2025年がいい年になりますように。
大晦日の紅白歌合戦、録画で高橋真梨子、矢野顕子&MISIAを見ました。
矢野顕子&MISIAの歌は希望に満ちていました。
高橋真梨子と矢野顕子は、私の車の中でよくかかります。
2人とも、20代からの大切なアーティストです。
高橋真梨子は、20歳の時、筑紫哲也さんの著書の中で知りました。
元旦は、穏やかな一日となりました。
この穏やかさが、一年続くといいですね。
2024年12月24日
新リース会計基準、加算金
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2025年1月号 ★
Merry Christmas , Happy Chiristmas . John Lennon の曲が流れています。
今年も一年、ありがとうございました。どうぞ来年もよいお年をお迎え下さい。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年1月の税務
1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)
新リース会計基準について
◆リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。
◆今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
過少申告・無申告でも加算金・重加算金は課されない
◆修正申告や更正決定処分があると
申告納税制度を担保するためとして、当初申告が過少申告だったり、無申告だったりした場合、ペナルティとして国税では加算税、地方税では加算金が課せられます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があります。過少申告加算税としては、追加本税の10%が課されますが、追加本税が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える場合は、その超過部分については、さらに5%追加加算されます。無申告加算税としては、納付すべき税額の50万円までについては15%、50万円超の部分については20%、300万円超の部分については30%が課されます。
◆仮装隠蔽・偽り不正の場合
上記の各加算税が課される場合で、仮装隠ぺいによる申告・無申告の場合には、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納税額の40%が重加算税として課されます。
◆遅延利息は更正決定無しに賦課
さらに、納税の遅延には、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。地方税では、延滞金と言います。
◆延滞金だけしか課せられない
ところで、地方税法での加算金、延滞金も、国税の加算税、延滞税と同じ性質なので、同じように課されるものと思いがちですが、住民税としての都道府県民税及び市町村民税の大部分には、延滞金は課されますが、加算金、重加算金は課されません。
加算金、重加算金が課せられる税の種類を地方税法で確認すると、分離課税に係る所得割、法人の事業税、配当割、株式等譲渡所得割、利子割、たばこ税、ゴルフ場利用税、環境性能割、鉱産税、入湯税、事業所税、水利地益税、特別土地保有税、軽油引取税、法定外普通税において条文規定があります。ここでは、分離課税とされる退職所得の住民税、法人事業税について規定の存在が確認できますが、法人住民税、個人住民税、個人事業税については、その規定が確認できません。
なぜかについては、法人住民税の課税標準が所得ではなく法人税額であり、法人税の附加税と性格付けされている、個人住民税・個人事業税が申告納税ではなく、賦課課税であることなどに理由がありそうです。
Merry Christmas , Happy Chiristmas . John Lennon の曲が流れています。
今年も一年、ありがとうございました。どうぞ来年もよいお年をお迎え下さい。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2025年1月の税務
1月10日
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
1月31日
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出
○給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)(1月中において市町村の条例で定める日)
新リース会計基準について
◆リース会計基準改正の公表
2024年9月13日、企業会計基準委員会が「リースに関する会計基準」の改正を公表しました。新基準は国際基準との整合性を図り、リース取引を財務諸表により正確に反映するためのものです。
◆新たなルールのポイント
今回の改正では、借手のすべてのリースを資産と負債に計上する「単一の会計処理モデル」を採用します。オペレーティング・リースを含むリース契約を「使用権資産」として資産計上し、リース料の支払い義務を「リース負債」として負債に計上することが求められます。これにより、リースの実態がより透明性を持って財務諸表に示されることになります。
◆適用日と早期適用について
新基準の適用開始日は2027年4月1日以降に始まる連結会計年度および事業年度からとなります。ただし、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。
◆すべてのリースを財務諸表に計上
新基準では、従来貸借対照表に計上されていなかったオペレーティング・リースも含め、すべてのリースが計上対象になります。これにより、リース取引の内容が財務諸表により正確に反映され、企業の資産・負債状況が明確に示されます。経営判断の透明性が高まり、財務報告の信頼性が向上する点が新たなルールの特徴です。
◆財務指標への影響に注意
リース負債の計上により、自己資本比率や負債比率などの財務指標に変動が生じる可能性があります。特に中小企業では、信用評価や金融機関との取引条件に影響を及ぼすことが予想されます。そのため、早めにリース契約や資金計画を見直し、新基準適用の影響を把握することが必要です。
◆今後の対応策
適用日までに十分な準備期間はありますが、早めの対応が求められます。まずは現在のリース契約を精査し、新基準に基づく会計処理の対象となるリースを特定しましょう。また、専門家と連携し、財務諸表への影響を最小限に抑える戦略を立てることも有効です。新基準への適切な対応は、企業の財務健全性を維持するために欠かせないものです。
過少申告・無申告でも加算金・重加算金は課されない
◆修正申告や更正決定処分があると
申告納税制度を担保するためとして、当初申告が過少申告だったり、無申告だったりした場合、ペナルティとして国税では加算税、地方税では加算金が課せられます。
加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税があります。過少申告加算税としては、追加本税の10%が課されますが、追加本税が期限内申告税額と50万円のどちらか多い方の金額を超える場合は、その超過部分については、さらに5%追加加算されます。無申告加算税としては、納付すべき税額の50万円までについては15%、50万円超の部分については20%、300万円超の部分については30%が課されます。
◆仮装隠蔽・偽り不正の場合
上記の各加算税が課される場合で、仮装隠ぺいによる申告・無申告の場合には、過少申告加算税の代わりに追加本税の35%、無申告加算税の代わりに納税額の40%が重加算税として課されます。
◆遅延利息は更正決定無しに賦課
さらに、納税の遅延には、原則として法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。地方税では、延滞金と言います。
◆延滞金だけしか課せられない
ところで、地方税法での加算金、延滞金も、国税の加算税、延滞税と同じ性質なので、同じように課されるものと思いがちですが、住民税としての都道府県民税及び市町村民税の大部分には、延滞金は課されますが、加算金、重加算金は課されません。
加算金、重加算金が課せられる税の種類を地方税法で確認すると、分離課税に係る所得割、法人の事業税、配当割、株式等譲渡所得割、利子割、たばこ税、ゴルフ場利用税、環境性能割、鉱産税、入湯税、事業所税、水利地益税、特別土地保有税、軽油引取税、法定外普通税において条文規定があります。ここでは、分離課税とされる退職所得の住民税、法人事業税について規定の存在が確認できますが、法人住民税、個人住民税、個人事業税については、その規定が確認できません。
なぜかについては、法人住民税の課税標準が所得ではなく法人税額であり、法人税の附加税と性格付けされている、個人住民税・個人事業税が申告納税ではなく、賦課課税であることなどに理由がありそうです。
2024年12月09日
電子帳簿保存法のその後
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2024年12月号 ★
クリスマスを控えて、街も活気づいております。
弊事務所のBGMもクリスマスソングになりました。
年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけて
お過ごしください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年12月の税務
12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
結局どうなった?電子取引データの保存方法
◆大騒ぎした電子帳簿保存法
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。
◆最低限の前に、求められていること
電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。
◆最低限必要なのは「できない理由」?
電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。
スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
◆雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か?
時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。
単発とはいえ、労働者を雇う以上、雇用側では、給与の源泉所得税の事務手続きと労働管理の取り扱いが発生します。
◆源泉徴収と年末調整、消費税
人材派遣の場合は、派遣される人の給与や労働管理は派遣元の会社が行います。派遣を受ける方(=働いてもらう会社)は派遣会社に外注費+消費税を支払うだけとなります。一方、スポットバイトの場合は、働いてくれる人とは労働契約を結び、給与を直接支払います。紹介(仲介)会社へは紹介料+消費税を支払います。給与の支払いも労働管理も雇い入れ側が行います。
給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。そのため、日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給することになります。
スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていません。そのため、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えて甲欄または乙欄適用に切り替えることや年末調整の対象となるといったことは、まずは考慮しなくて構いません。
◆社会保険と労働保険の適用
2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険の手続きは不要です。
スキマバイトは労働者ですので、雇用側での労務管理が必要です。正規に勤務先を持っていて副業として働いている場合など、それぞれの事業場の労働時間を通算して管理しなければなりません。また、仲介会社が2社以上の場合はさらに複雑となります。雇う側は、やらなければならない業務やリスクを把握し、働く人が安心・安全に働けるよう労務管理を徹底しなければなりません。こうなるともう、社会保険労務士にサポートしてもらうことをお勧めします。
クリスマスを控えて、街も活気づいております。
弊事務所のBGMもクリスマスソングになりました。
年末に向けご多忙のことと存じますが、健康にお気をつけて
お過ごしください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年12月の税務
12月10日
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(6月〜11月分)の納付
翌年1月6日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
○給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)
結局どうなった?電子取引データの保存方法
◆大騒ぎした電子帳簿保存法
電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。
実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。
◆最低限の前に、求められていること
電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。
可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規定の制定と遵守です。要するに取引データをPCで検索できるようにしておくのと、データの訂正や削除をする際の規定を作っておきなさい、ということです。
ただし、検索要件については、2課税年度前の売上高が5,000万円以下か、電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理してあり、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば不要です。
◆最低限必要なのは「できない理由」?
電子取引データの保存の要件を満たせない場合でも「猶予措置」が設けられていて、その要件は「ルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所属税務署長が相当の理由があると認める場合」と「税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めか、電子取引データを印刷したものの提示や提出の求めに応じることができるようにしている場合」を満たしていることです。ちなみに「相当の理由」について事前申請等は不要です。
つまり、「人手不足」「資金不足」「システム整備が間に合わない」等のできない理由の準備と、電子取引データを消さないように保存しておけば、現状最低限、電子取引データの保存については大丈夫ということになります。
ただ、経理のICT化・DX化は生産性UPにも繋がります。電子帳簿保存についても、自社のタイミングでルール策定やシステム改修をご検討ください。
スポットバイトの課税と労働管理等(雇用会社側の観点から)
◆雇用側・労働側双方に魅力ありの形態か?
時代を映す鏡ともいわれるテレビ広告で、最近、“すき間時間に単発で働こう!”といった雇用の形をよく目にします。雇う側では、“忙しい時にだけ単発でほしい働き手を、長期雇用責任の縛りなく、確保できる”から、一方の働く側では、“働きたいときだけ、履歴書を提出する採用面接を受けずに働けるし、給料もすぐに受け取れる”からといった理由が背景にあるようです。
単発とはいえ、労働者を雇う以上、雇用側では、給与の源泉所得税の事務手続きと労働管理の取り扱いが発生します。
◆源泉徴収と年末調整、消費税
人材派遣の場合は、派遣される人の給与や労働管理は派遣元の会社が行います。派遣を受ける方(=働いてもらう会社)は派遣会社に外注費+消費税を支払うだけとなります。一方、スポットバイトの場合は、働いてくれる人とは労働契約を結び、給与を直接支払います。紹介(仲介)会社へは紹介料+消費税を支払います。給与の支払いも労働管理も雇い入れ側が行います。
給与の支払いは時給もしくは日給で労働日ごとに支払われます(=日雇い賃金)ので、源泉徴収票は丙欄の適用となります。そのため、日額が9,300円以上の支払いから源泉所得税を差し引いて支給することになります。
スポットバイトはそもそも短期の雇用で継続性を前提としていません。そのため、2か月を超えたらその時点から正式雇用に切り替えて甲欄または乙欄適用に切り替えることや年末調整の対象となるといったことは、まずは考慮しなくて構いません。
◆社会保険と労働保険の適用
2か月を超えない短期労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象外です。そのため、社会保険の手続きは不要です。
スキマバイトは労働者ですので、雇用側での労務管理が必要です。正規に勤務先を持っていて副業として働いている場合など、それぞれの事業場の労働時間を通算して管理しなければなりません。また、仲介会社が2社以上の場合はさらに複雑となります。雇う側は、やらなければならない業務やリスクを把握し、働く人が安心・安全に働けるよう労務管理を徹底しなければなりません。こうなるともう、社会保険労務士にサポートしてもらうことをお勧めします。
2024年10月22日
M&A対価の損金算入
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2024年11月号 ★
秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年11月の税務
11月11日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
12月2日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
M&A対価の損金算入が7割から10割に
◆M&A損失準備金7割損金算入部分
令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。
◆併存枠の創設とその対象と要件
これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。
さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。
◆取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違
なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。
◆併存新枠適用に必要なM&A過去実績
新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。
◆新たな追加要件も改正項目
それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。
過去契約の保険はこの項目の対象外です。
従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
◆従業員の住所変更時の社会保険の手続き
社会保険に加入している会社で、従業員から転居等により住所変更をした旨の知らせがあった場合は、所定の届出が必要です。「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を年金事務所に届けます。そして、住所変更を届け出る従業員に被扶養配偶者がいる場合、上記届出書と一緒に「国民年金第3号被保険者住所変更届」も提出します。これらの届出書は、持参・郵送・電子申請のいずれかで手続きします。
なお、社会保険とマイナンバーの紐づけができている従業員については、住所変更の手続きをする必要はありません。
適正に住所変更をしておかないと、年金に関する重要な通知(「ねんきん定期便」など)が本人に届かなくなったり、必要な本人確認ができなくなったりしますので、遅滞ない届出が必要です。
◆給与計算(所得税計算)のための住所変更
住所の変更そのものが毎月の給与計算に影響を与えることはありませんが、住所の変更に伴い扶養家族が増えたり減ったりすることも少なくありません。扶養家族の人数が変われば毎月の源泉所得税の計算にも影響してきます。住所変更があった場合は、改めて「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告扶養控除等申告書」を提出してもらうか、変更箇所の書き直しを、遅滞なくしてもらってください。
◆住民税の届け出は必要か?
住所変更先がこれまでとは違う他の市区町村となる場合によくある質問が、「住民税の特別徴収の変更手続きは必要か?」という問い合わせです。
結論から言うと、住民税の特別徴収は当年1月1日に居住していた自治体(=旧住所)に課税権があり続けますので、変更届は不要です。年の途中に他の市区町村に引っ越ししても、住民税の納付先(=会社が給与から特別徴収して会社が納付する)は変わりません。
新しい住所先での住民税は、会社が各従業員の翌年1月1日に住所地がある自治体に「給与支払報告書」を1月末までに提出し、それをもとに新住所のある自治体で課税が始まります。年末調整確認用の「扶養控除等(異動)申告書」に正しい現住所の記載があれば、翌年から適正に住所地のある自治体から住民税が課税されることになります。
秋も深まり、冷え込んで参りました。
お風邪など召されませぬようお願い申し上げます。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年11月の税務
11月11日
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
11月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
12月2日
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人事業税の納付(第2期分)(11月中において都道府県の条例で定める日)
M&A対価の損金算入が7割から10割に
◆M&A損失準備金7割損金算入部分
令和6年度税制改正で、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた中小企業(資本金額1億円以下の法人又は従業員数1000人以下の個人企業、但し大規模法人関連法人等は除外)に適用される、M&A10億円以下株式取得価額の70%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立額の損金算入の制度は、3年間の期間延長とされています。
◆併存枠の創設とその対象と要件
これと併存する形で、産業競争力強化法の特別事業再編計画の認定を受けた中小企業・中堅企業(従業者数2000人以下企業)が、M&A株式取得価額(1億円以上100億円以下)の90%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その額を損金算入出来るとの制度が創設されました。
さらに同じ認定を受けた次の別のM&Aにより株式取得(1億円以上100億円以下)をする場合、その取得価額の100%以下の中小企業事業再編投資損失準備金積立をすると、その全額の損金算入が認容されます。
◆取崩しに係る従前枠と併存新枠の相違
なお、従前制度の積立額は5年経過後の事業年度から5年間で均等取崩し益金算入ですが、新制度の積立額は10年経過後の事業年度から5年間での均等取崩し益金算入です。
◆併存新枠適用に必要なM&A過去実績
新創設の併存新枠適用には、過去5年以内にM&Aの実績があることとの条件が改正産業競争力強化法に規定されているので、その要件充足も必要です。それは既存の7割損金算入のM&Aの適用実績に限定されるものではなく、実際のM&Aの経験実績でよく、法律文は「他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得を行っていること」となっています。
◆新たな追加要件も改正項目
それから、M&A損害保険契約を締結している場合は、損金算入制度適用除外であり、事後に当該保険契約を締結した場合は、過去計上の中小企業事業再編投資損失準備金を含め、即座に取崩し、全額益金算入しなければならないことになりました。
過去契約の保険はこの項目の対象外です。
従業員に住所変更があった場合の社会保険と税金の手続き
◆従業員の住所変更時の社会保険の手続き
社会保険に加入している会社で、従業員から転居等により住所変更をした旨の知らせがあった場合は、所定の届出が必要です。「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を年金事務所に届けます。そして、住所変更を届け出る従業員に被扶養配偶者がいる場合、上記届出書と一緒に「国民年金第3号被保険者住所変更届」も提出します。これらの届出書は、持参・郵送・電子申請のいずれかで手続きします。
なお、社会保険とマイナンバーの紐づけができている従業員については、住所変更の手続きをする必要はありません。
適正に住所変更をしておかないと、年金に関する重要な通知(「ねんきん定期便」など)が本人に届かなくなったり、必要な本人確認ができなくなったりしますので、遅滞ない届出が必要です。
◆給与計算(所得税計算)のための住所変更
住所の変更そのものが毎月の給与計算に影響を与えることはありませんが、住所の変更に伴い扶養家族が増えたり減ったりすることも少なくありません。扶養家族の人数が変われば毎月の源泉所得税の計算にも影響してきます。住所変更があった場合は、改めて「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告扶養控除等申告書」を提出してもらうか、変更箇所の書き直しを、遅滞なくしてもらってください。
◆住民税の届け出は必要か?
住所変更先がこれまでとは違う他の市区町村となる場合によくある質問が、「住民税の特別徴収の変更手続きは必要か?」という問い合わせです。
結論から言うと、住民税の特別徴収は当年1月1日に居住していた自治体(=旧住所)に課税権があり続けますので、変更届は不要です。年の途中に他の市区町村に引っ越ししても、住民税の納付先(=会社が給与から特別徴収して会社が納付する)は変わりません。
新しい住所先での住民税は、会社が各従業員の翌年1月1日に住所地がある自治体に「給与支払報告書」を1月末までに提出し、それをもとに新住所のある自治体で課税が始まります。年末調整確認用の「扶養控除等(異動)申告書」に正しい現住所の記載があれば、翌年から適正に住所地のある自治体から住民税が課税されることになります。
2024年09月21日
交際費から除外される接待飲食費、同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2024年10月号 ★
いまだ暑さが残ります今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年10月の税務
10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
交際費から除外される接待飲食費の金額基準
◆令和6年度の交際費に係る改正
令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とされています。例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではなく、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1万円基準で判定して適用することになっています。
◆交際費課税は決済日での判定ではない
クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額を算定することになります。つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用することになります。
◆法人規模別の交際費課税の内容
因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。
◆交際費での接待飲食費
接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のために要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれます。
交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。
◆交際費除外計算のための適用要件
接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要求されています。
一 飲食年月日
二 飲食参加者名と関係
三 飲食参加者数
四 飲食額、店名、所在地
五 飲食事実の明示事項
同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
借地権が設定された被相続人の土地は、相続税では「貸宅地」とされ、自用地価額から借地権価額を控除した金額で評価します。
◆通常の地代の場合は、財産評価通達で評価
土地の使用の対価として通常、権利金を収受する慣行のある地域で通常の賃貸借契約により通常の地代を支払うとき、貸宅地は財産評価通達により評価されます。
なお、通常の地代未満の地代を支払う場合も以下の算式で評価します。
●貸宅地の価額=自用地価額×(1-借地権割合)
◆同族会社に貸付けする場合の評価
被相続人が同族関係者となっている同族会社にアパート経営をさせるため、自分の土地に借地権を設定する場合、借地契約を第三者との取引と異なる条件で行うと権利金等と実際の地代の水準に応じて借地権と貸宅地の評価は影響を受けます。
以下は、権利金等の支払がない場合です。
(1) 相当の地代を支払っている場合
権利金の認定課税を回避するため、権利金の支払に代えて相当の地代を支払う場合、借地権評価額は零、貸宅地の評価額は自用地価額の80%となります。
(2) 通常の地代を超え、相当の地代未満
貸宅地の価額は、実際に支払う地代の水準に応じて決まります。
●貸宅地の価額=自用地価額-自用地価額×借地権割合×{1-(実際の地代-通常の地代)/(相当の地代-通常の地代)}
ただし、貸宅地の価額が自用地価額の80%を超える場合は、被相続人が借地契約により土地利用の制約を受けていたことを考慮して80%を上限とします。
なお、(1)(2)とも、20%分は同族会社の借地権として同族会社の株式評価上、純資産価額に算入されます。
◆小規模宅地等の特例による評価減
さらに一定の要件を満たすと「貸宅地」は「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例が適用されます(200㎡まで50%減)。同族会社との賃貸借契約の締結、地代の支払(有償貸付)が前提となります。ただし、固定資産税程度の地代設定では営利性が認められず、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることはできません。適用には相続開始前3年を超えて被相続人等の貸付事業の用に供されていること(特定貸付事業は3年以内も可)、事業承継要件、保有継続要件を満たすことが必要です。
いまだ暑さが残ります今日この頃、
いかがお過ごしでしょうか。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年10月の税務
10月10日
●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10月15日
●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10月31日
●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
交際費から除外される接待飲食費の金額基準
◆令和6年度の交際費に係る改正
令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される接待飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下(改正前5000円以下)に引き上げられました。物価高や経済活動の活性化の観点からの改正とのことから、従来のように事業年度単位での適用関係ではなく、税制改正法施行日の令和6年4月1日から即適用とされています。例えば、12月決算法人であっても、次期の期首日以降の適用ではなく、今期の期中中途である令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費から、1万円基準で判定して適用することになっています。
◆交際費課税は決済日での判定ではない
クレジットカード等での支払いの場合で、令和6年4月1日以後の支払いであったとしても、接待飲食等の行為があった時が同年3月以前である時は、1万円基準での判定とすることにはならず、従前の5000円基準で判定して、交際費の額を算定することになります。つまり、接待飲食等の実行日ベースで適用することになります。
◆法人規模別の交際費課税の内容
因みに、交際費についての措置法の規定は、資本金百億円超の法人では全額損金不算入、資本金1億円超の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%が損金算入、資本金1億円以下の法人では交際費のうちの接待飲食費の50%か、年800万円の定額控除限度額かが損金算入、とされています。
◆交際費での接待飲食費
接待飲食費とは、得意先等を接待して行う飲食その他これに類する行為のために要する費用で、飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料なども含まれます。
交際費除外計算新基準の1万円は、1人当たりの接待飲食費の金額が1万円以下の場合での適用であり、1万円を超える場合は、1万円までが交際費除外対象となるのではなく、その全額が交際費等に該当するものとされます。
◆交際費除外計算のための適用要件
接待飲食費の交際費除外の適用要件として次の事項を記載した書類の保存が要求されています。
一 飲食年月日
二 飲食参加者名と関係
三 飲食参加者数
四 飲食額、店名、所在地
五 飲食事実の明示事項
同族会社が借主の場合の貸宅地の評価
借地権が設定された被相続人の土地は、相続税では「貸宅地」とされ、自用地価額から借地権価額を控除した金額で評価します。
◆通常の地代の場合は、財産評価通達で評価
土地の使用の対価として通常、権利金を収受する慣行のある地域で通常の賃貸借契約により通常の地代を支払うとき、貸宅地は財産評価通達により評価されます。
なお、通常の地代未満の地代を支払う場合も以下の算式で評価します。
●貸宅地の価額=自用地価額×(1-借地権割合)
◆同族会社に貸付けする場合の評価
被相続人が同族関係者となっている同族会社にアパート経営をさせるため、自分の土地に借地権を設定する場合、借地契約を第三者との取引と異なる条件で行うと権利金等と実際の地代の水準に応じて借地権と貸宅地の評価は影響を受けます。
以下は、権利金等の支払がない場合です。
(1) 相当の地代を支払っている場合
権利金の認定課税を回避するため、権利金の支払に代えて相当の地代を支払う場合、借地権評価額は零、貸宅地の評価額は自用地価額の80%となります。
(2) 通常の地代を超え、相当の地代未満
貸宅地の価額は、実際に支払う地代の水準に応じて決まります。
●貸宅地の価額=自用地価額-自用地価額×借地権割合×{1-(実際の地代-通常の地代)/(相当の地代-通常の地代)}
ただし、貸宅地の価額が自用地価額の80%を超える場合は、被相続人が借地契約により土地利用の制約を受けていたことを考慮して80%を上限とします。
なお、(1)(2)とも、20%分は同族会社の借地権として同族会社の株式評価上、純資産価額に算入されます。
◆小規模宅地等の特例による評価減
さらに一定の要件を満たすと「貸宅地」は「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例が適用されます(200㎡まで50%減)。同族会社との賃貸借契約の締結、地代の支払(有償貸付)が前提となります。ただし、固定資産税程度の地代設定では営利性が認められず、「小規模宅地等の特例」の適用を受けることはできません。適用には相続開始前3年を超えて被相続人等の貸付事業の用に供されていること(特定貸付事業は3年以内も可)、事業承継要件、保有継続要件を満たすことが必要です。
2024年08月22日
宅地と隣接する駐車場の評価単位
★ 川口明彦税理士事務所 事務所だより 2024年9月号 ★
暦では夏の終わりと申しながら、まだまだ暑い日がつづきますね。
夏の疲れが出てくる頃です。
体調管理には充分気をつけてお過ごしください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年9月の税務
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
宅地と隣接する駐車場の評価単位
相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません。
評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決める基本ルールは、次のものとなります。
◆土地は地目ごとに区分される
土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に区分されます。「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地とされます。「雑種地」は、どの地目にも属さない土地とされ、駐車場の敷地は「雑種地」となります。
土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合、そのうち主たる地目からなるものとして評価します。
◆宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する
宅地は利用の単位となる1区画の宅地(1画地の宅地といいます)ごとに評価します。
同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは自宅の維持・効用を果たすために必要なものとして、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」として自用地評価します。
◆土地の評価に他人の権利が及ぶ場合
土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地として評価します。
賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの住人だけが使用する場合、建物と駐車場の土地は一体利用されているので一画地の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。
◆月極駐車場を経営する場合は自用地評価
土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為とされ、賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係となります。この場合、土地評価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。
なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業者の権利が土地に及びますので減価されます。
従業員の育休取得時の対応
◆問題の背景
育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月に改正が行われたのに続き、今後も性別を問わず、育児休業を取得しやすくするための改正が予定されています。
一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業員が育児休業を取得した場合の業務の代替をどうするかなど問題が残されています。とは言え、育児休業の取得は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはできません。従業員が育児休業を取得している間の業務の代替に関しては、早急に検討する必要があると考えられます。
◆体制整備について
従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、大きく2つのポイントが考えられます。(1)取得のパターンごとに留意すべき点があること。(2)どのパターンで取得しても困らない体制づくりを目指すこと。令和4年4月及び10月の改正によって、育児休業を取得するパターンが多様化しています。それぞれのパターンでの取得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙げてみます。
(ア) 連続した日数を長期間取得する場合
子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得するケースなどがあたります。休業が長期間となる場合には、1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い段階での業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が長時間労働になり不満やストレスが溜まらないよう、可能な限り複数人数で分担することなどが望ましい対応と考えられます。
(イ) 短期間や分割で取得する場合
令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業制度の創設」など、男性が育児休業を取得しやすくするための改正が、数多く行われました。このことにより、男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回に分けて取得したりするケースが増えています。このケースでの注意点は、出生時育児休業を取得しようとする従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出ればよいことになっているため、業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎを短期間で行わなければなりません。このような事態を避けるため、事前に制度についての個別周知を行い、早めに本人の意向を確認する必要があります。
暦では夏の終わりと申しながら、まだまだ暑い日がつづきますね。
夏の疲れが出てくる頃です。
体調管理には充分気をつけてお過ごしください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
2024年9月の税務
9月10日
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
宅地と隣接する駐車場の評価単位
相続で土地を評価する場合、土地をどこで区切るかを決めなければなりません。
評価のために区切られる土地の1つ1つを評価単位と言います。評価単位を決める基本ルールは、次のものとなります。
◆土地は地目ごとに区分される
土地は用途によって、「宅地」「田」「畑」「山林」「雑種地」などの地目に区分されます。「宅地」は、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地とされます。「雑種地」は、どの地目にも属さない土地とされ、駐車場の敷地は「雑種地」となります。
土地は地目別に評価するのが原則ですが、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合、そのうち主たる地目からなるものとして評価します。
◆宅地や雑種地は利用の単位ごとに評価する
宅地は利用の単位となる1区画の宅地(1画地の宅地といいます)ごとに評価します。
同じ土地に居宅と隣接する自家用の駐車スペースがある場合、駐車スペースは自宅の維持・効用を果たすために必要なものとして、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
マンションとマンションの住人だけが利用する隣接の駐車場の場合も同様に、敷地全体を「宅地」として自用地評価します。
商業施設に併設する駐車場の敷地は、商業施設と一体利用されるので「宅地」として自用地評価します。
◆土地の評価に他人の権利が及ぶ場合
土地を他人に使用させる場合は、土地の評価には他人の権利が及びます。
賃貸アパートや賃貸マンションの敷地は、住人の権利が及ぶため、貸家建付地として評価します。
賃貸アパートや賃貸マンションに隣接する駐車場は、アパートやマンションの住人だけが使用する場合、建物と駐車場の土地は一体利用されているので一画地の宅地となり、全体を貸家建付地として評価します。
◆月極駐車場を経営する場合は自用地評価
土地所有者が自身で月極駐車場を運営する場合は、車の保管を目的とする行為とされ、賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係となります。この場合、土地評価に利用者の権利は及ばず、自用地評価となります。
なお、コインパーキングなど駐車場事業者に土地を賃貸する場合は、その事業者の権利が土地に及びますので減価されます。
従業員の育休取得時の対応
◆問題の背景
育児・介護休業法については、令和4年の4月と10月に改正が行われたのに続き、今後も性別を問わず、育児休業を取得しやすくするための改正が予定されています。
一方で、多くの企業で人材不足の悩みは深刻で、従業員が育児休業を取得した場合の業務の代替をどうするかなど問題が残されています。とは言え、育児休業の取得は労働者の権利であり、企業は原則として拒むことはできません。従業員が育児休業を取得している間の業務の代替に関しては、早急に検討する必要があると考えられます。
◆体制整備について
従業員が育児休業を取得する際の体制整備については、大きく2つのポイントが考えられます。(1)取得のパターンごとに留意すべき点があること。(2)どのパターンで取得しても困らない体制づくりを目指すこと。令和4年4月及び10月の改正によって、育児休業を取得するパターンが多様化しています。それぞれのパターンでの取得に応じた体制整備が必要になります。いくつか例を挙げてみます。
(ア) 連続した日数を長期間取得する場合
子供が出生後1歳に達するまで育児休業を取得するケースなどがあたります。休業が長期間となる場合には、1年間の業務を見据えた対応が必要になり、早い段階での業務の引き継ぎや、業務を代替する要員が長時間労働になり不満やストレスが溜まらないよう、可能な限り複数人数で分担することなどが望ましい対応と考えられます。
(イ) 短期間や分割で取得する場合
令和4年4月及び10月の改正では、「出生時育児休業制度の創設」など、男性が育児休業を取得しやすくするための改正が、数多く行われました。このことにより、男性が2週間程度の育児休業を取得したり、休業を数回に分けて取得したりするケースが増えています。このケースでの注意点は、出生時育児休業を取得しようとする従業員は、原則として2週間前までに職場に申し出ればよいことになっているため、業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎを短期間で行わなければなりません。このような事態を避けるため、事前に制度についての個別周知を行い、早めに本人の意向を確認する必要があります。